スマホ・デジタル機器と
子どもの脳発達
便利なスマホやタブレット。
使い方次第で学びの味方にも、睡眠不足や注意散漫の引き金にもなります。
WHO・AAP のガイドラインや最新脳科学研究を踏まえ、年齢別の影響と家庭でできる整え方をまとめました。
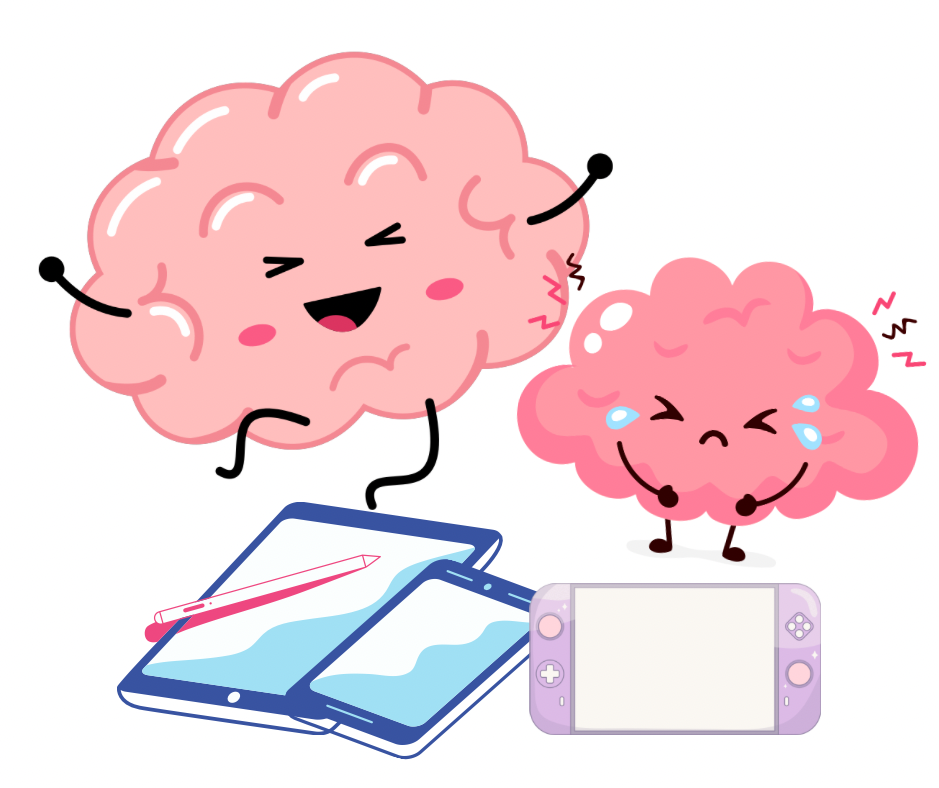
年齢別
スクリーンタイムと脳への影響
年齢:0〜1歳
推奨スクリーンタイム目安:
0 分(ビデオチャットを除く)
0 分(ビデオチャットを除く)
脳・心への主な影響:
視覚・聴覚の感受性期に 言語入力が減少
視覚・聴覚の感受性期に 言語入力が減少
ポイント:
親子の対面コミュニケーション優先
親子の対面コミュニケーション優先
年齢:1〜2歳
推奨スクリーンタイム目安:
同席視聴のみ
同席視聴のみ
脳・心への主な影響:
操作性より受動視聴 → 注意分散
操作性より受動視聴 → 注意分散
ポイント:
短時間で歌やリズム遊びアプリを一緒に
短時間で歌やリズム遊びアプリを一緒に
年齢:2〜5歳
推奨スクリーンタイム目安:
1時間/日
1時間/日
脳・心への主な影響:
前頭前野発達期にテンポ早い刺激で衝動性↑
前頭前野発達期にテンポ早い刺激で衝動性↑
ポイント:
15 分×4 回など分割+高品質教育コンテンツ
15 分×4 回など分割+高品質教育コンテンツ
年齢:6〜12歳
推奨スクリーンタイム目安:
2時間/日
2時間/日
脳・心への主な影響:
シナプス刈り込み期に 睡眠時間減少 で学習効率↓
シナプス刈り込み期に 睡眠時間減少 で学習効率↓
ポイント:
宿題後のご褒美タイム+就寝 1 時間前はオフ
宿題後のご褒美タイム+就寝 1 時間前はオフ
年齢:13〜18歳
推奨スクリーンタイム目安:
2〜3 時間/日(学習除く)
2〜3 時間/日(学習除く)
脳・心への主な影響:
報酬系敏感期で ドパミン過剰刺激 →依存リスク
報酬系敏感期で ドパミン過剰刺激 →依存リスク
ポイント:
SNS 使用ルールを共同制定&週末はデジタルデトックス
SNS 使用ルールを共同制定&週末はデジタルデトックス
脳科学が示す3つの注意点
| ブルーライトとメラトニン抑制: 就寝2時間前の画面は睡眠ホルモン低下 |
|---|
| 報酬回路の過活動: ゲームの即時報酬はドパミン放出→他課題の動機づけ低下 |
| 視覚過多によるワーキングメモリ負荷: 高速動画は情報処理スピードと注意切替を過度に要求 |
家庭でできる7つのルール
| スクリーンフリーゾーンの設定: 寝室・食卓はノーデジタル |
|---|
| 20-20-20ルール: 20分使用→20秒間 20ft(約6 m)先を眺め目休憩 |
| 共視聴・共遊び: 幼児は大人の対話で語彙・感情ラベリングアップ |
| コンテンツは質を優先: 教育系・クリエイティブ系をリスト化 |
| 就寝前1時間はデバイスオフ: ブルーライトカット+交感神経クールダウン |
| 休日はデジタルデトックスデー: 公園・読書・ボードゲームで五感刺激 |
| 親も実践: 大人の姿が最強のモデル |
赤信号サインと相談の目安
| 夜型化で学校遅刻・欠席が続く |
|---|
| 端末を取り上げると激しい癇癪 |
| 視力低下・肩こり・頭痛の慢性化 |
| 学業・友人関係よりオンライン優先 |
当院では生活リズム評価とデジタルデトックス支援を行っています。
当院からのメッセージ
デジタル機器は“良薬にも毒にも”。
脳と心の発達段階を意識し、質・時間・環境を整えれば学びの強力なツールになります。
使いすぎが心配なときは、お気軽に発達外来へご相談ください。
よくあるご質問
Q. “知育アプリ” は長時間でも大丈夫?
A. 受動視聴より良いですが、連続 30 分以内が目安です。
Q. ブルーライトカット眼鏡で夜のスマホはOK?
A. 光だけでなく興奮刺激も睡眠を妨げるため就寝前はオフが推奨です。
Q. 親がスマホを使う仕事なので難しい…
A. 家族で“使わない時間帯”を30分でも設定し、まずは小さく始めましょう。
Q. みよし市からも利用できますか?
A. はい、みよし市から車で約20分、駐車場完備です。
【この記事の監修・執筆】
アイキッズクリニック
院長 会津 研二(小児科専門医)
新生児・発達・思春期の診療に長年携わり、
多くのお子さんの成長と自立を見守ってきました。
ご家庭や集団生活でも穏やかに過ごせるよう、
アドバイスや治療をご提案しています。
お気軽にご相談ください。








