吃音
(Stuttering)
「ぼ、ぼ、ぼく…」「——えっと…」とことばが詰まる状態を吃音(スタッタリング)と呼びます。
発症は2〜5歳が最多で、約5%の子どもが経験し、75%は自然に改善しますが、持続・悪化する場合は早期の支援が有効です。
当院では、医師による評価と支援プログラムを提供しています。
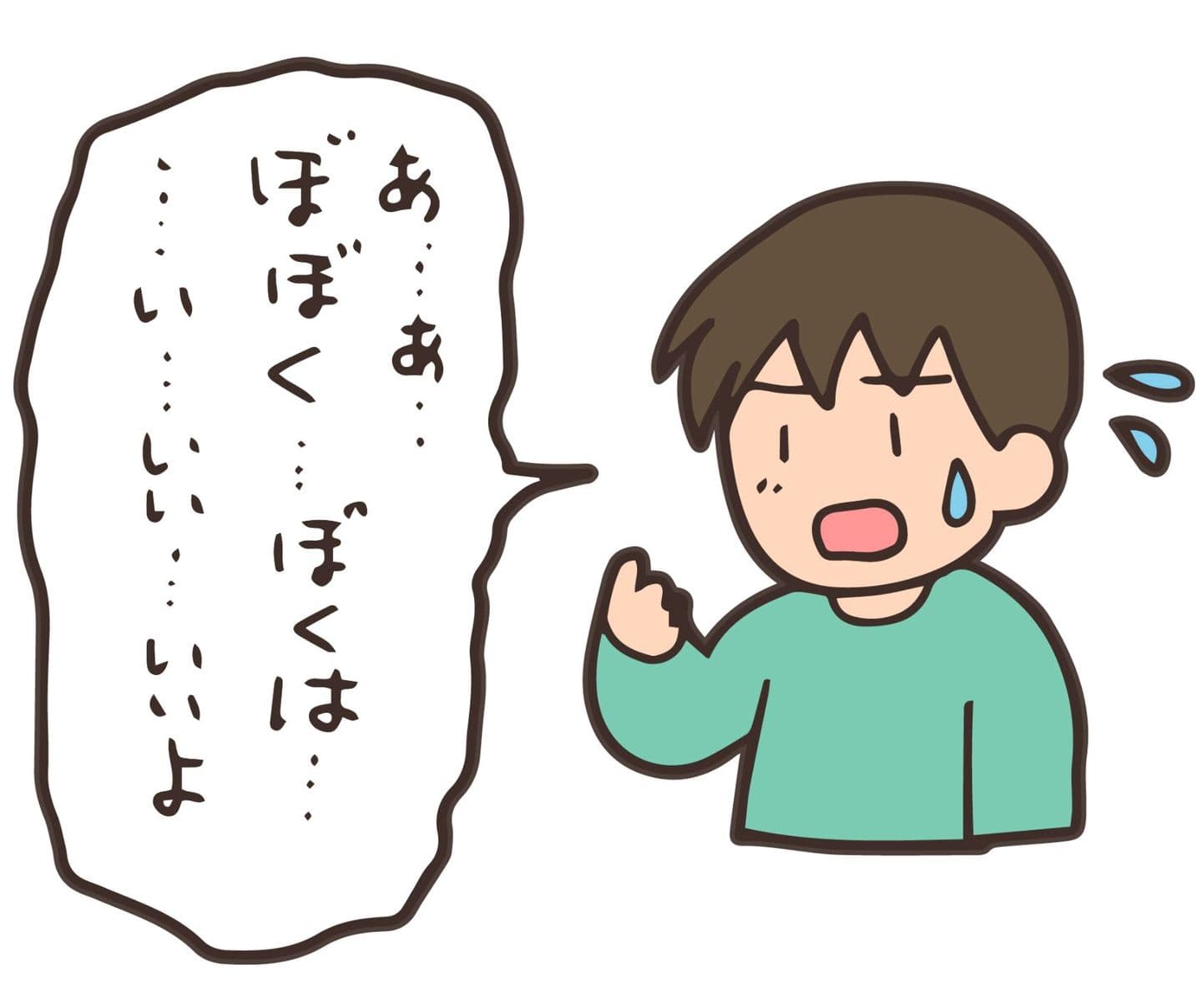
吃音のタイプと特徴
| タイプ | 具体例 |
|---|---|
| 音・音節の繰り返し | 「かかか…傘」 |
| 音の引き伸ばし | 「かーーさ」 |
| ブロック (語頭で無音停止) |
「…傘」 |
症状の前に予期不安や表情のこわばりが伴うことがあります。
発症要因とリスク因子
| 遺伝:吃音がある子どもの27.4%に家族に吃音経験者(吃音がない子どもは10.4%) |
|---|
| 性別:男児に多い(男女比 3〜4:1) |
| 器質的要因:脳の言語流暢性ネットワーク(弓状束など)の異常 |
| 発達的要因:運動・認知・言語・情緒が爆発的に発達する時期の影響(たくさんの言葉を獲得する過程で、「話したい」気持ちがその子の発話能力を超えてしまうなど) |
| 体質的要因:子ども自身が生来的に持つ吃音になりやすい体質(遺伝であって育て方による問題ではない) |
| 環境要因:周囲の人との関係や生活上の出来事 |
これらの要因のうち、体質的要因が7~8割程度と言われています。
評価の流れ
| 医師初診: 発症時期・頻度・状況・家族歴を聴取 |
|---|
| リスク判定: 発症~現在までの変化、リスク要因の確認 |
| 併存症の確認: 自閉スペクトラム症やADHDなどその他の疾患が併存していないか |
支援・治療プログラム
| 基本は経過観察: 自然治癒の可能性が高いため、環境調整や保護者への情報提供が中心 |
|---|
| 発症から1年以上経過している・リスク要因がみられる場合:介入を検討 |
年齢や症状の段階、心理的な問題などに応じて都度支援を変更する必要があります。
家庭でできるサポートの例
| 話し方のアドバイスをしない: 「ゆっくり」「落ち着いて」などの声掛けはプレッシャーにつながり逆効果なことも |
|---|
| 聞き切る姿勢: 最後まで言わせ、焦らず待つ |
| 保護者がゆっくり話しかける: 周囲がゆっくりと話しかけ自然に真似をするように仕向ける |
| 十分な睡眠とリラックス: 疲労・緊張を減らす |
当院からのメッセージ
吃音は早期の理解と温かな環境で、ことばの自信を育むことができます。
「様子を見るだけで大丈夫かな?」と迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 親の話し方が原因?
A. 原因は神経発達と遺伝が主体で、育て方が直接原因ではありません。
Q. 何歳まで様子を見ても良い?
A. 3 歳半を超えて持続・悪化する場合やブロック型がある場合は早期評価をおすすめします。
Q. 学校への配慮は?
A. 読み上げ順を調整、発表形態の選択肢を増やすなど合理的配慮を依頼します。
Q. みよし市在住でも通院できますか?
A. はい、みよし市から車で約20分、駐車場完備です。
【この記事の監修・執筆】
アイキッズクリニック
院長 会津 研二(小児科専門医)
新生児・発達・思春期の診療に長年携わり、
多くのお子さんの成長と自立を見守ってきました。
ご家庭や集団生活でも穏やかに過ごせるよう、
アドバイスや治療をご提案しています。
お気軽にご相談ください。








